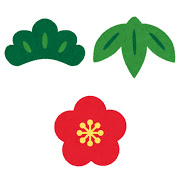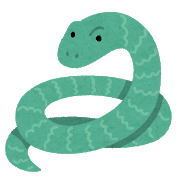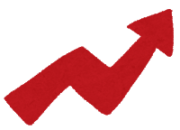「松竹梅」という言葉は、元々中国の「歳寒三友」として知られていました。
この言葉は、松と竹と梅の三つを指しており、それぞれ冬の厳しさに耐える特性を持つため、これらの植物は中国で「歳寒の三友」として称えられ、よく画の題材として取り上げられました。
この考え方が日本に伝わり、各々の植物が持つ象徴的な意味がさらに深まった。
平安時代には、松が長寿や不老不死を意味するようになりました。
室町時代には、竹が子孫繁栄のシンボルとして捉えられるようになり、そして江戸時代には、梅が気高さや長寿を象徴するものとして認識されるようになりました。
現代において「松竹梅」は、品質や等級を示す際の言葉としても使用されますが、もともとこの三つの植物には優劣の区別は存在しなかったのです。
しかし、言葉の響きから「松」が最上級とされ、その次に「竹」と「梅」が続く、という順序で解釈されることが多くなりました。
【松竹梅】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 原語「歳寒三友」 | 中国起源の言葉。冬の厳しさに耐える松、竹、梅の三つの植物を指し、よく画の題材として取り上げられた。 |
| 日本での象徴的意味 | 松は平安時代に長寿や不老不死、竹は室町時代に子孫繁栄、梅は江戸時代に気高さや長寿を象徴するものとして認識された。 |
| 現代での使用 | 品質や等級を示す言葉として使われるが、元々の意味ではこれらの植物間に優劣は存在しなかった。 |
| 「松竹梅」の順序 | 言葉の響きから、現代では「松」が最上級とされ、次に「竹」と「梅」が続くという順序で解釈されることが多い。 |