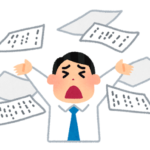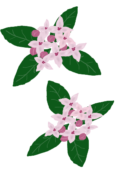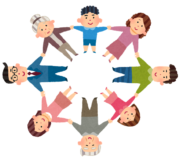将棋は、古代インドの遊戯であるチャトランガが原型とされています。
このチャトランガは時間とともに様々な地域に伝わり、形を変えて広まっていきました。
西洋ではチェスとして知られるようになり、中国ではシャンチー(象棋)として、朝鮮半島ではチャンギ(將棋)として発展しました。
日本に将棋が伝わったのは、中国を経由してのことでした。
その影響から、名称も中国語の「象棋・象戯」を基にして名付けられました。
この「象棋・象戯」を日本語で音読すると「しょうぎ」となり、それがそのまま遊戯の名前として使われるようになりました。
さらに、この名称を表記する際には、「将棋」という漢字が使用されるようになりました。
【将棋・象棋・象戯】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 将棋の原型 | 古代インドの遊戯「チャトランガ」が原型。 |
| チャトランガの広がり |
|
| 将棋の日本への伝来 | 中国を経由して日本に伝わり、「象棋・象戯」が名称の基となった。 |
| 「将棋」の名前の由来 | 「象棋・象戯」を日本語で音読すると「しょうぎ」となり、これが遊戯の名前として使われた。さらに、「将棋」という漢字で表記されるように。 |