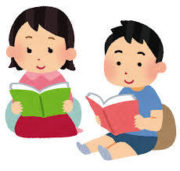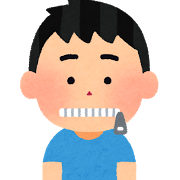「おかあさん(御母さん)」という言葉は、江戸時代末期に上方、すなわち大阪や京都などの中流階級以上の家庭で、子供たちが母親を呼ぶ言葉として使われ始めました。
この言葉が全国的に普及する大きなきっかけは、明治36年(1903年)に尋常小学校の教科書に採用されたことです。
それ以前に、特に江戸(現在の東京)では「おっかさん」という形で母を呼ぶことが多かったようです。
しかし、教科書で「おかあさん」が採用されたことにより、この表現が全国に広まり、現在では多くの日本人が用いる一般的な言葉となりました。
この言葉は、現代でも子供が自分の母親を呼ぶ場合や、夫が妻を呼ぶ場合などに多用されています。
また、その意味はさらに広がり、義母や母代わりに慕う人、さらには大人の女性に対しても使われることがあります。
【御母さん】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「おかあさん(御母さん)」に関する基本的な情報とその用途、意味の拡大をカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 言葉の起源 | 江戸時代末期の上方(大阪、京都など)で中流階級以上の家庭で使われ始めた。 |
| 普及のきっかけ | 明治36年(1903年)に尋常小学校の教科書に採用されたこと。 |
| それ以前の表現 | 江戸(現在の東京)では「おっかさん」と呼ばれていた。 |
| 現代での用途 | 子供が母親を呼ぶ、夫が妻を呼ぶなど、多用されている。 |
| 意味の拡大 | 義母や母代わりに慕う人、大人の女性に対しても使われることがある。 |