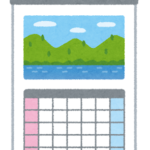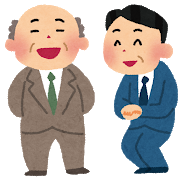「言葉」という言葉は、非常に深い歴史と意味を持っています。
もともと「言葉」を意味する言葉としては「言」が一般的でしたが、上代の日本では「事」と「言」、つまり「事柄」と「言葉」の間に明確な区別がありませんでした。
このため、「言」には重要な事実や意味を持ったものとして捉えられていました。
しかし、時間が流れるにつれて、単に口で言うだけの、事実や実体を伴わない軽い意味を「言」に持たせる必要が生じました。
そこで、「端」という言葉が付け加えられ、「ことば」という言葉が生まれました。
この「ことば」という新しい言葉は、徐々に言語そのものや言葉を表現する語として広く使われるようになりました。
さらに、奈良時代には、「言葉」、「言羽」、「辞」という三つの言葉が使われており、特に「言羽」は比較的軽い言葉として捉えられていました。
平安時代には、「ことば」、「詞」、「言葉」という三つの表現が存在していました。
そして、私たちが今日「言葉」として認識している漢字の表記が残ったのは、和歌の背景にある考え方によるものです。
和歌は、人の心の中に芽生えた想いが「言の葉」として成長し、その木が豊かに葉をつけるものと考えられていました。
この「葉」が豊かであることは、言葉そのものが豊かであることを意味し、それが「言葉」という表記が残る理由となったのです。
ことば【言葉】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「言葉」の意味の変遷や異なる時代の表現方法、そして「言葉」の漢字表記が残った背景についての主要なポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初期の意味 | 「言」は重要な事実や意味を持ったものとして捉えられていた。 |
| 「ことば」の成立 | 「端」が付加されて「ことば」が生まれ、言葉を表現する語として広く使われるようになった。 |
| 奈良時代の表現 | 「言葉」、「言羽」、「辞」の三つが使われ、「言羽」は軽い意味の言葉として捉えられていた。 |
| 平安時代の表現 |
|
| 「言葉」の漢字表記の残存 | 和歌の背景にある「言の葉」の考え方から。「葉」が豊かであることは言葉そのものが豊かであることを意味し、「言葉」という表記が残った。 |