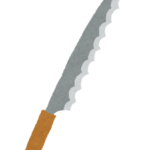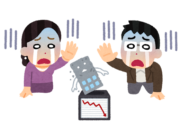「気障(キザ)」という言葉は、もともと「きざわり(気障り)」という形で江戸時代の遊郭で使用されていました。
当時は女郎が男性客に対して使う言葉で、主に「心にかかり、苦になること」を意味していました。
このような背景から、基本的には男性に対して用いられる語として確立されました。
時が経過するにつれて、この言葉は変化して「人に不快感を与える」、特に「服装・態度・行動などが気取っていて、人に不快や反感を感じさせること」という意味に拡大していきました。
つまり、元々は心の負担や苦しみを表す言葉であったものが、後には人々に不快感を与えるような気取りやいやみを指すようになったのです。
キザ【気障】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「気障(キザ)」の語源とその意味に関する主要なポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 初期形 | 「きざわり(気障り)」 – 心にかかり、苦になることを意味 |
| 初期の使用状況 | 江戸時代の遊郭で、女郎が男性客に対して使う言葉 |
| 語の進化 | 時間が経つと、「人に不快感を与える」などの意味に拡大 |
| 現在の意味 | 服装・態度・行動などが気取っていて、人に不快や反感を感じさせること |
| 性別の関連性 | 基本的には男性に対して用いられる語として確立された |