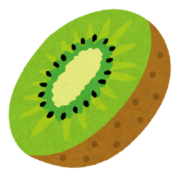「吉方巻き」または「恵方巻」は、主に日本で節分の日に食べられる巻き寿司です。
この名前の「吉方」という部分は、陰陽道の考えに基づいて、その年の干支によって定められた「吉」とされる方角、すなわち「恵方」を指しています。
風習としては、この恵方に向かって黙って願い事を唱えながら、巻き寿司を丸ごと一つ食べるというものです。
この「丸ごと食べる」という行為は、縁を切らないという縁起をかつぐためとされています。
この風習が一般に広まった背景には、1970年代半ばに大阪海苔問屋協同組合が、寿司関係の団体と連携して節分に恵方巻きを食べるという販売促進活動を行った影響が大きいです。
そのため、今日では多くの人々が節分にこの吉方巻きを食べる文化が確立しています。
一方で、この風習の正確な起源については不明な点が多く、江戸時代末期に大阪の船場で商売繁盛や無病息災を願って食べたのが始まりとされていますが、詳細ははっきりしていないとされています。
要するに、「吉方巻き」は陰陽道の考えに基づいて恵方に向かって食べる巻き寿司であり、縁起をかついで願い事を叶えるための風習として広まっています。
そして、近年では特に節分と密接に関連づけられ、多くの人々に楽しまれている文化となっています。
【吉方巻き】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 名前の由来 | 陰陽道の考えに基づいて、吉とされる方角(恵方)を指す |
| 食べる行為の意味 | 恵方に向かって黙って願い事を唱え、丸ごと食べる |
| 縁起 | 丸ごと食べることで縁を切らないという縁起をかつぐ |
| 広まりの背景 | 1970年代に大阪海苔問屋協同組合が販売促進活動を行った影響 |
| 現代の関連性 | 節分と密接に関連づけられ、多くの人々に楽しまれている |
| 歴史的背景 | 江戸時代末期の大阪船場で始まったとされるが、詳細は不明 |