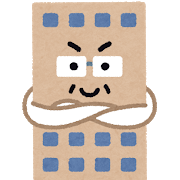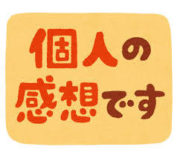「十八番」という言葉は、もともと歌舞伎から生まれたもので、「歌舞伎十八番」として知られています。
この「歌舞伎十八番」とは、歌舞伎の市川家が得意としていた、特に人気のある狂言18の演目を指す言葉です。
ここでの「番」は、能や狂言の演目を数えるときの単位として使われます。
この「歌舞伎十八番」には、「外郎売」「嫐」「押戻」など、18の有名な演目が含まれています。
これらの演目は、市川家にとって特に得意であり、そのためこの言葉が使われるようになりました。
さらに、「十八番」という言葉は、「おはこ」とも読まれるようになりました。
これは、「歌舞伎十八番」の台本を大切に保存するために箱に入れて保管され、次の世代に受け継がれていったことに由来します。
その箱に鑑定家の署名があり、それが「箱書き」と呼ばれました。
そして、その「箱書き」を持つ芸が真作と認定され、その認定された芸を指して「おはこ」と言うようになったのです。
これらの経緯から、「十八番」は現在では、得意なものや最も自信を持っているものを指す言葉として使われるようになりました。
【十八番】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「十八番」という言葉の起源、初期の意味、現代での使用方法などの主要なポイントをカンタンにまとめます。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 起源 | 歌舞伎の「歌舞伎十八番」 |
| 初期の意味 | 歌舞伎の市川家が得意とする、特に人気のある狂言18の演目 |
| 「番」の意味 | 能や狂言の演目を数えるときの単位 |
| 代表的な演目 | 「外郎売」「嫐」「押戻」などの18の演目 |
| 「おはこ」の由来 | 「歌舞伎十八番」の台本を大切に保存するための箱に関連して |
| 現代の使用 | 得意なものや最も自信を持っているものを指す |