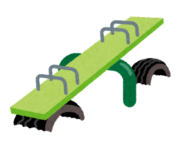「一辺倒(いっぺんとう)」という表現は、どちらか一方に偏る、もしくは一方的にかたよる状態を指します。
この言葉の語源は、北宋時代の中国の儒者、程顥(ていこう)に遡ります。
程顥は自身の教えに対して盲目的に従う学生、特に謝顕道という人物を批判するためにこの表現を使いました。
彼は「一辺を救い得れば、一辺に倒れ了わる。ただ人の一辺に執着せんことを怕るのみ」という言葉で、一つの観点に固執するのではなく、多角的に物事を考えるよう諭しました。
この教えは、『近思録』という書籍に記されています。
この表現が広く知られるようになったのは、第二次世界大戦後に毛沢東がこの言葉を論文で引用したことです。
毛沢東の影響で、この四字熟語は広く流布し、現在では多くの文脈で用いられています。
つまり、「一辺倒」は、程顥の古典的な教えから出発し、その後、毛沢東によって再評価されて広まった表現です。
その背後には、一方的な考えに偏らず、多面的な視点を持つ重要性という教訓があります。
【一辺倒】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「一辺倒」の意味、語源、古典的な文脈と現代的な文脈、そしてその背後にある重要な教訓についてカンタンにまとめます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 意味 | どちらか一方に偏る、もしくは一方的にかたよる状態を指す |
| 語源 | 北宋時代の中国の儒者、程顥がこの表現を使い、自身の教えに対して盲目的に従う学生を批判 |
| 古典的な文脈 | 程顥は『近思録』という書籍で、一辺倒の考え方を避け、多角的に物事を考えるよう諭した |
| 現代的な文脈 | 第二次世界大戦後、毛沢東がこの表現を論文で引用し、広く流布した |
| 重要な教訓 | 一方的な考えや視点に偏らず、多面的な視点を持つ重要性が強調される |