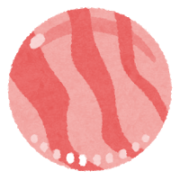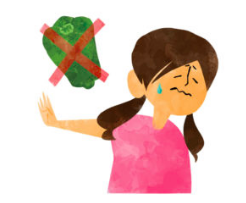「赤」という言葉は、多様な意味や用途を持つ日本語の単語ですが、その語源は「明か(あか)」と同じであり、元々は「明るい」を意味します。
この「明るい」感覚は、特に「暗し(くらし)」や「黒(くろ)」と対照的な概念として理解されています。
このため、「赤」には「明らか」や「全く」、「すっかり」といったニュアンスも含まれています。
例えば、「赤恥」や「赤の他人」といった言葉に見られるように、「全くの他人」や「完全な恥」などの意味で用いられます。
また、古代の日本においては、「赤」が単独で用いられるよりも複合語として使用されることが多く、色を指す際には「朱(あけ)」という単語が一般的でした。
漢字の「赤」は、上部に「大」、下部に「火」を組み合わせています。
この組み合わせは、大きく燃え上がった火を象徴しており、それが「赤」という色に対応しています。
総じて、「赤」という単語はその語源、由来を通じて多層的な意味を持っており、色、状態、概念など多方面で用いられています。
【赤】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「赤」の語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 語源 | 「明か(あか)」と同じで、元々は「明るい」を意味する。 |
| 対照概念 | 「暗し(くらし)」や「黒(くろ)」と対照的。 |
| 追加のニュアンス | 「明らか」や「全く」、「すっかり」といった意味も含む。 |
| 例 | 「赤恥」や「赤の他人」など、完全な恥や全くの他人を意味する。 |
| 古代の用途 | 単独での使用より複合語としての使用が多く、「朱(あけ)」が色を指す一般的な単語だった。 |
| 漢字の構成 | 上部に「大」、下部に「火」。大きく燃え上がった火を象徴し、それが「赤」色に対応する。 |
| 多層的な意味 | 語源や由来を通じて多層的な意味を持つ。色、状態、概念など多方面で用いられている。 |