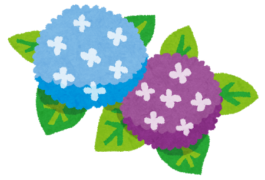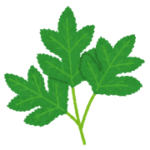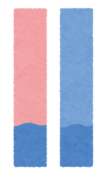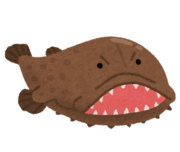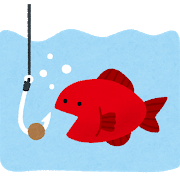紫陽花(アジサイ)の語源についてはいくつかの説がありますが、定かではありません。
古い文献によると、万葉集では「味狭藍」や「安治佐為」というような形で表記されていました。
また、平安時代の『和名類聚抄』では「阿豆佐為」と記されています。
これらの表記を考慮に入れると、「あづさい(集真藍)」という言葉が時間の経過とともに「アジサイ」として一般化した可能性があるとされています。
この「あづさい」は、藍色が集まったもの、すなわち多くの青い花が集まって咲く様子を意味していると言われています。
漢字で「紫陽花」と表記されるのは、実は誤りから来ているとされています。
この漢字は、唐の詩人である白居易がライラックと考えられる花に付けた名前です。
平安時代の学者、源順がこの漢字をアジサイに当てたことで、このように広く認識されるようになりました。
総じて、アジサイの名前には歴史的な経緯と多少の混乱が含まれていますが、それが今日でも多くの人々に愛される美しい花であることには変わりありません。
【紫陽花】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、アジサイの名前と歴史に関わる重要なポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明・詳細 |
|---|---|
| 旧表記 | 万葉集では「味狭藍」や「安治佐為」、『和名類聚抄』では「阿豆佐為」と表記。 |
| 語源の一説 | 「あづさい(集真藍)」が時代とともに「アジサイ」として一般化した可能性あり。 |
| 「あづさい」の意味 | 藍色が集まったもの、すなわち多くの青い花が集まって咲く様子。 |
| 漢字表記「紫陽花」の由来 | 実は誤り。唐の詩人、白居易がライラックに付けた名前が平安時代に誤ってアジサイに当てられた。 |
| 現在の認識 | 名前に歴史的な経緯と混乱があるが、美しい花として多くの人々に愛されている。 |