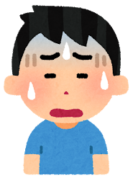「美しい」という日本語の語は、時間を経て多くの変遷を遂げています。
この言葉はもともと肉親、特に子供や配偶者など、自分よりも弱い存在に対する愛情や慈しみを表す言葉として使われていました。
例えば、古い文献である「万葉集」には、「妻子(めこ)見ればめぐし(かわいらしいし)」という形で登場しています。
この段階では「美しい」という言葉は、一般的な美の概念というよりは、愛情に対する「心が引かれる」「いとしい」といった感じ方を主に表していました。
平安時代に入ると、この言葉は幼いものや小さなものがかわいらしいという意味でも用いられるようになります。
例として、「竹取物語」では「三寸ばかりなる人、いとうつくいうてゐたり」とあり、小さなものに対する可愛らしさ、愛らしさを表す言葉としても用いられました。
平安時代が進むと、この言葉はさらに一般的な「きれい」や美的なものを表すように変化しました。
この意味の変遷は室町時代にかけて確立し、現在の「美しい」という言葉に繋がっています。
漢字の「美」に関しては、「羊+大」という形から成り立っており、この組み合わせは古代中国で特に大切にされた家畜である羊を、形のよい大きな存在として表しています。
要するに、「美しい」の語源は初めては「慈しみ」や「愛情」に注目していたものが、時代と共に「一般的な美」へと意味が拡大していったのです。
【美しい】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「美しい」という言葉の重要なポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 詳細・内容 |
|---|---|
| 初期の用途 | 肉親や弱い存在に対する愛情や慈しみを表す。万葉集で「心が引かれる」「いとしい」など。 |
| 平安時代① | 幼いものや小さなものがかわいらしいという意味で使われるように。竹取物語で例示。 |
| 平安時代② | 一般的な「きれい」や美的なものを表すように変化。この意味は室町時代に確立。 |
| 漢字の由来 | 「羊+大」から成り立っており、形のよい大きな存在(羊)を表している。 |
| 意味の拡大 | 初めては「慈しみ」や「愛情」から、時間とともに「一般的な美」へと意味が拡大。 |