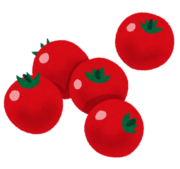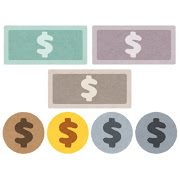「床の間」とは、座敷の一部を一段高くしたスペースで、正面の壁に書画や掛け軸を掛け、床板の上には置物や花瓶などを飾る場所を指します。
この空間は、室内の中心的な装飾の場所として、特に重要な位置を占めています。
この「床の間」の名称の起源は、室町時代の書院造に伴い出現した「押板(おしいた)」にあります。
押板は、特定の物を置くための高くされたスペースで、主に高炉や花瓶、燭台など、いわゆる三具足を置く場所として利用されていました。
江戸時代に入ると、この押板は「床(とこ)」という名前で呼ばれるようになりました。
この時期、上層の農民や町人の住居にも「床」が取り入れられるようになったのです。
そして、明治時代に入ると、更に一般の家庭でも「床」が普及し、この時期から「床の間」という名前で広く知られるようになりました。
とこのま【床の間】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 定義 | 座敷の一部を一段高くしたスペース。書画や掛け軸、置物や花瓶などを飾る場所 |
| 位置 | 室内の中心的な装飾の場所 |
| 起源 | 室町時代の「押板(おしいた)」 |
| 押板の利用 | 高炉、花瓶、燭台(三具足)を置く場所として |
| 江戸時代 | 「押板」が「床(とこ)」と呼ばれ、上層の農民や町人の住居にも採用される |
| 明治時代 | 一般の家庭で「床」が普及し、「床の間」という名前で広く知られるようになる |