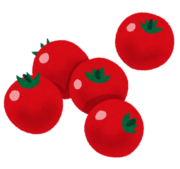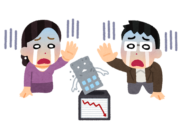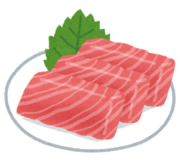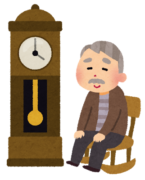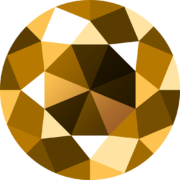トマトの名前は、英語の「tomato」を元にしていますが、その起源はメキシコの先住民言語であるナワトル語の「tomatl」にあります。
「tomatl」はホオズキの果実を意味しており、メキシコではトマトは「xitimate」や「xitomatl」として知られています。
ここでの「xi」は皮がむけたり、丸いという意味を持っています。
ヨーロッパへは、スペインの探検家エルナン・コルテスがトマトの種を持ち帰ったことで伝わりました。
彼らは「tomatl」を基に「tomate」と呼びましたが、スペイン語の「-o」語尾や、ジャガイモを意味する「potate」との響きの関係から、英語では「tomato」という名前が定着しました。
日本においては、1670年頃の江戸時代の寛文年間に長崎を通じて初めて紹介されましたが、初めは観賞用としての導入であり、食用としての普及はそれより後のことです。
「トマト」の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| トマトの名前の起源 | ナワトル語の「tomatl」 |
| 「tomatl」の意味 | ホオズキの果実 |
| メキシコでの名称 |
|
| 「xi」の意味 | 皮がむけたり、丸い |
| ヨーロッパへの伝播 | エルナン・コルテスが種を持ち帰った |
| スペイン語での名称 | 「tomate」 |
| 英語での名称 | 「tomato」 |
| トマトの日本への紹介 | 1670年頃、江戸時代の寛文年間、長崎を通じて |
| 日本での初期の用途 | 観賞用 |
| 日本での食用普及 | 1670年頃の紹介後 |