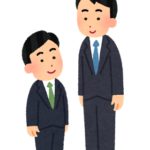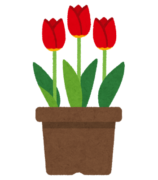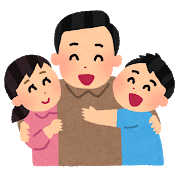「ちまき」は、端午の節句に食べられる糯米粉や粳米粉、葛粉などで作られた餅のことを指します。
この餅は、長円錐の形に固められ、笹や真菰(まこも)の葉で巻かれ、藺草で縛られて蒸し上げられます。
この伝統的な食べ物の起源は、中国にあります。
伝説によれば、詩人の屈原が汨羅川に投身した後、彼の姉が彼を追悼するために、端午の節句に餅を川に投げ入れて祀ったのが始まりとされています。
「ちまき」という名前の由来は、古くからこの餅を「茅(ちがや)」の葉で巻いていたことに関係しています。
日本への伝来は古く、奈良時代にはすでに知られていたと考えられており、平安時代には宮中の行事としても行われていました。
この名前は、その特徴的な巻き方、特に「茅」の葉を使って巻かれていたことにちなんで名づけられました。
ちまき【粽】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明・内容 |
|---|---|
| 名称 | ちまき |
| 主成分 |
|
| 形状 | 長円錐の形、笹や真菰の葉で巻かれ、藺草で縛られて蒸し上げ |
| 起源 | 中国 |
| 伝説の背景 | 詩人の屈原が汨羅川に投身後、彼の姉が端午の節句に餅を川に投げ入れて祀った |
| 名前の由来 | 「茅(ちがや)」の葉で巻いていたことに関連 |
| 日本への伝来 | 奈良時代に知られ、平安時代に宮中の行事としても行われた |