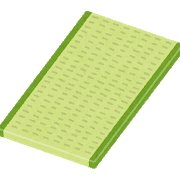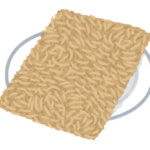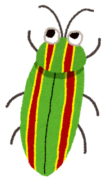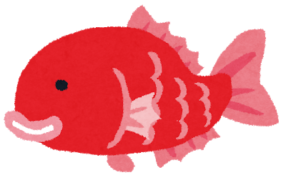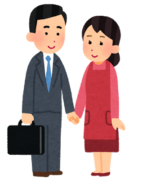畳(たたみ)という言葉は、もともと「たたむこと」を意味しています。
この「たたむ」という動作から、何かを折り返して重ねる、つまりたためる物、敷物のすべてを指すようになりました。
この名前の由来は、敷物を使わないときには折りたたんでしまうことからきているのです。
この「たたむこと」という意味が名詞として定着し、「たたみ」という言葉になりました。
畳の使用の歴史を見ると、古くは「厚畳」と称され、部屋の中には板張りの床の上に寝台として設置して使用されていました。
しかし、部屋全体を畳で覆うような使い方は、中世以降に普及しました。
このスタイルは、特に書院造りの家や寺院などでよく見られるようになったのです。
たたみ【畳】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「畳(たたみ)」の語源や背景に関する重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明・内容 |
|---|---|
| 現代での意味 | 敷物、部屋の床を覆う材料。 |
| 語源 | 「たたむこと」からきており、折り返して重ねる物や敷物全般を指すようになった。 |
| 名前の由来 | 敷物を使用しないときに折りたたむことから。 |
| たたみの成立 | 「たたむこと」という意味が名詞として定着し、「たたみ」という言葉になった。 |
| 歴史的背景 | 古くは「厚畳」として、寝台として板張りの床の上に使用。中世以降、部屋全体を畳で覆う使い方が普及。 |
| 使用の特徴 | 書院造りの家や寺院などで、部屋全体を畳で覆うスタイルが一般的になった。 |