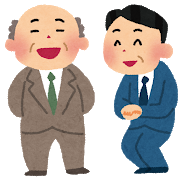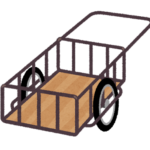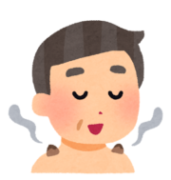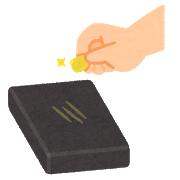「太鼓持ち」という言葉の由来は、江戸時代の遊郭の風景からきています。
遊郭での酒宴では、客の機嫌をとりながら宴を盛り上げる役目を担っていた男たちがいました。
彼らは客の機嫌を取るのが主な仕事で、「太鼓持ち」や「幇間(ほうかん)」と呼ばれていました。
さらに、「太鼓」には、調子に合わせて打つという性質があります。
この性質から、太鼓持ちが客の気分や要望に合わせて行動する様子が、「調子のよいお世辞」や人の気を引く行為を指す意味として太鼓持ちという言葉が使われるようになりました。
このように、太鼓持ちという言葉は、他人の機嫌を取ることを主とする人を指す言葉として現代に伝えられています。
【太鼓持ち】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「太鼓持ち」という言葉の意味や起源に関する重要なポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 言葉の起源 | 江戸時代の遊郭の風景 |
| 遊郭における「太鼓持ち」 | 宴を盛り上げ、客の機嫌をとる役目を担う男たち。別名「幇間(ほうかん)」とも呼ばれる |
| 「太鼓」の性質 | 調子に合わせて打つ |
| 現代の意味 | 他人の機嫌をとる行為や調子のよいお世辞を言う人を指す |