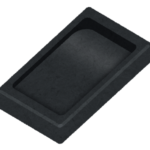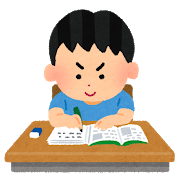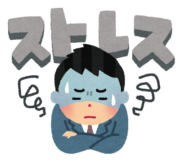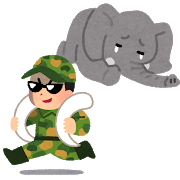「雀鮨」は、元々は江鮒という魚を使って作られる料理で、この魚の腹の中にすし飯を詰めて形を作るものでした。
この料理の特徴的な部分は、すし飯を詰めた魚の腹が膨らんで見える点です。
この膨らんでいる姿が、雀のように見えるとされたことから、この料理に「雀鮨」という名前がつけられました。
時代が進んで、現代では小鯛を使用することが多くなりましたが、名前の由来やその特徴は変わっていません。
特に、大阪や和歌山ではこの雀鮨が名物として親しまれています。
すずめずし【雀鮨】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「雀鮨」に関する主要な情報やその特徴・背景をカンタンにまとめます。
| 項目名 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 雀鮨 |
| 元々の主材料 | 江鮒(こえぶな) |
| 調理方法 | 魚の腹の中にすし飯を詰めて形を作る。 |
| 名前の由来 | すし飯を詰めた魚の腹が膨らんでおり、その姿が雀に似ているため。 |
| 現代の主材料 | 小鯛 |
| 特徴 | 名前の由来や調理方法の特徴は変わっていない。 |
| 地域の名物 | 大阪や和歌山で名物として親しまれている。 |