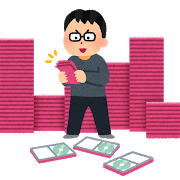「助六鮨」という名前の由来は、歌舞伎の作品「助六」に関連しています。
「助六」は、主人公・助六が宝刀を探すために吉原に出入りし、遊女の揚巻と恋に落ちるという物語です。
この遊女の名前「揚巻」から、名前の「揚げ」を油揚げの稲荷鮨に、そして「巻」を海苔巻きに関連付け、その二つを組み合わせた鮨の名前として「助六鮨」という名前がつけられました。
さらに、助六がハチマキを頭に巻いていたことから、その「ハチマキ」を海苔巻きに、そして「揚巻」を油揚げに見立てたとも言われています。
では、なぜ「揚巻鮨」ではなく「助六鮨」という名前が使われるようになったのでしょうか。
これについては、いくつかの説があります。
一つの説としては、江戸っ子の遊び心や洒落から、物語の主人公「助六」の名前を取り入れて「助六鮨」としたと言われています。
また、歌舞伎の幕間に助六鮨が弁当として出されたため、その名が定着したという説も存在します。
このように、歌舞伎と食文化が交錯する中で、「助六鮨」という名前が生まれたのです。
【助六鮨】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「助六鮨」という名前の起源や由来、さらには名前が定着した背景などの情報をカンタンにまとめます。
| 主要ポイント | 詳細・例 |
|---|---|
| 「助六鮨」の起源 | 歌舞伎の作品「助六」から。 |
| 名前の由来 | 遊女「揚巻」の名前から「揚げ」を油揚げの稲荷鮨、そして「巻」を海苔巻きに関連付けた名前。助六の「ハチマキ」も関連しているとされる。 |
| 「揚巻鮨」ではない理由 |
|
| 「助六鮨」の名の定着 | 歌舞伎と食文化の交錯の中で、この名前が生まれ定着した。 |