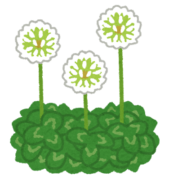「鹿」は日本語で「シカ」と読みますが、この言葉の起源は非常に興味深いものがあります。
古い時代には、鹿のことを単に「カ」と称していました。
そして、雌の鹿を「メカ」と、雄の鹿を「シカ」と呼んで区別していました。
この「シ」は「夫」を意味する「セ」から変化したものとされており、一方で「メ」は「女」を指しています。
つまり、元々の「シカ」は雄の鹿を意味していたのです。
しかし、時代が経過するにつれて、「シカ」という言葉が雌の鹿をも指すようになりました。
この変化に伴って、新たな名称も生まれました。
雄の鹿は「オジカ」、雌の鹿は「メジカ」と呼ばれるようになったのです。
このように、言葉の変遷を辿ることで、「シカ」という言葉の背景や、それがどのように進化してきたのかを理解することができます。
シカ【鹿】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「シカ」の名前に関する由来や変遷をカンタンにまとめます。
| 属性 | 詳細 |
|---|---|
| 対象の言葉 | シカ |
| 古代の呼称 |
|
| 「シ」の由来 | 「夫」を意味する「セ」から変化 |
| 「メ」の意味 | 「女」 |
| 元々の意味 | シカは雄の鹿を指す |
| 時間の経過による変化 | シカが雌の鹿も指すようになる |
| 新しい呼称 |
|