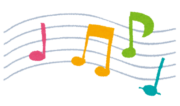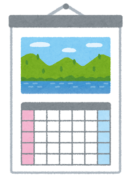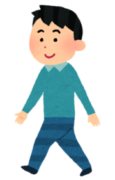「御年玉」は、新年に贈るお祝いの品で、特に現代では子供や目下の人にお金を贈る習慣として一般的です。
語源については、最初は正月に歳神を迎えるための儀式で、丸い鏡餅を供えて子供たちに分け与えたところから来ています。
この餅は歳神様の御霊が宿ると考えられ、そのため「御歳魂(おとしだま)」と呼ばれました。
また、「御歳玉」や「年賜(としだま)」とも呼ばれ、これは年のありがたい「賜物(たまもの)」という意味からきています。
この習慣自体は中世以降に見られ、その当時は武士が太刀を、医者が丸薬を贈るなど、職業によって異なる贈り物がされていました。
現代のように主にお金を贈る習慣は、昭和30年代以降に一般的になったとされています。
御年玉の背後には、歳神様への感謝とその神秘を子供たちと共有するという、古い日本の信仰と習慣が基盤となっています。
その後、時代とともに形が変わってもその精神は今日まで続いています。
おとしだま【御年玉】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 基本的な意味 | 新年に贈るお祝いの品で、特に子供や目下の人にお金を贈る習慣。 |
| 語源 | 歳神を迎える正月の儀式で供えた鏡餅が分け与えられ、それが「御歳魂(おとしだま)」と呼ばれた。また、年の「賜物(たまもの)」とも。 |
| 歴史的背景 | 中世以降に始まり、職業によって異なる贈り物がされていた。 |
| 現代の状況 | 昭和30年代以降、お金を贈る習慣が一般的になった。 |
| 精神的・文化的背景 | 年神様への感謝とその神秘を子供たちと共有する古い日本の信仰と習慣が基盤。形は変わっても、その精神は続いている。 |