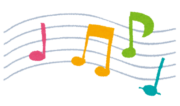「大盤振舞」は日本文化における饗宴や招待の形態を指す言葉ですが、この表現は実は当て字であり、正確には「椀飯振舞」と書き、「おうばんぶるまい」と読みます。
「椀飯」は椀に盛った飯を指し、この言葉は「わんばん」から「おうばん」と音が変化しています。
この表現は、時代や文化によってその使われ方が変わっています。
元々は公家社会で行われる饗宴を指していました。
中世の武家社会では、大名が輪番で将軍に祝膳を奉る行事を指していました。
近世になると、一家の主人が正月などの特別な機会に親類縁者を招いて御馳走を振る舞うことを意味するようになりました。
このように、時代や文化によって具体的な形が異なるものの、一貫して「盛大な饗応」を提供するという意味で用いられています。
【大盤振舞】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「大盤振舞」の基本的な意味、語源と読み方、時代的な変遷、そして共通のテーマをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 基本の意味 | 盛大な饗宴や招待の形態を指す。 |
| 語源・読み方 | 当て字で「大盤振舞」と書くが、正確には「椀飯振舞」と書き、「おうばんぶるまい」と読む。 |
| 時代的変遷 | 元々は公家社会の饗宴、中世では大名が将軍に祝膳を奉る行事、近世では一家の主人が親類縁者を招いての御馳走を意味する。 |
| 共通のテーマ | 時代や文化によって形は異なるが、一貫して「盛大な饗応」を提供するという意味で用いられている。 |