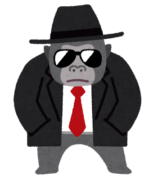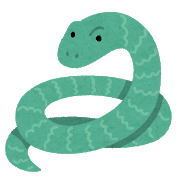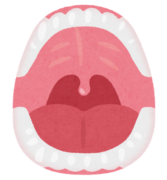「くつ」または「靴・沓・履」という言葉は、足を保護し、歩行を助けるための具です。
この言葉の語源には複数の説があります。
一つの説は、「ケルタル(蹴足)」という言葉が変化したものであるという点です。
もう一つの説は、足を靴の中に納める様子を象徴する擬態語「クツ」から来ているというものです。
また、朝鮮語の「kuit(グドゥ)」から来ているとする説も存在しますが、確定的な情報はまだありません。
歴史的な側面で見ると、最古の履物は紀元前7000年頃に作られたアメリカの樹皮製のサンダルであるとされています。
日本では、古墳時代の金銅製の履物や、奈良時代に正倉院に保管されている「繍線鞋」といった室内用の靴が有名です。
言葉それぞれには特定の文脈や歴史があり、「沓」は主に日本古来の様々な種類の履物を指すとされています。
一方で「靴」は、明治時代以降、西洋文化とともに普及した革の靴を指すようになりました。
総じて、「くつ」や「靴・沓・履」は、時間や地域、文化によってその形や意味が多様化してきた言葉であり、それぞれの時代や文化背景に根ざした多くのバリエーションが存在すると言えます。
くつ【靴・沓・履】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「くつ(靴・沓・履)」の語源から歴史、日本と西洋での違い、多様性に至るまで、多角的な視点でその特性と意味をカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明・特徴 |
|---|---|
| 基本の意味 | 足を保護し、歩行を助けるための具 |
| 語源の説 | 「ケルタル(蹴足)」から来たという説、擬態語「クツ」から来たという説、朝鮮語の「kuit(グドゥ)」から来たという説など |
| 最古の履物 | 紀元前7000年頃、アメリカの樹皮製のサンダル |
| 日本の歴史的な履物 | 古墳時代の金銅製の履物、奈良時代の「繍線鞋」など |
| 「沓」と「靴」の違い | 「沓」は日本古来の履物を指し、「靴」は明治以降、西洋の革の靴を指すようになった |
| 多様性 | 時間、地域、文化によって形や意味が多様化してきた |