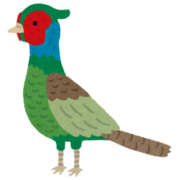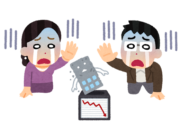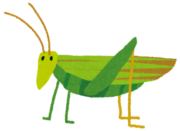「キジ」、または漢字で表記する場合は「雉・雉子」、はキジ目キジ科に属する鳥であり、特に日本では国鳥としても選定されています。
この鳥の語源は、古称の「キギシ」に由来しています。
この名称は平安時代から使われており、時代が下るにつれて「キギス」とも呼ばれるようになりました。
「キギス」の末尾の「ス」は、他の鳥の名前にも見られる接尾語であり、この「ス(シ)」は鳥を表すものとして朝鮮語に由来するとされています。
例えば、「カラス」や「ウグイス」でもこの接尾語が用いられています。
漢字での表記「雉子」は、主に「キギス」や「キギシ」を指すために使われています。
このように、名前の変遷を通じて「キジ」は多様な呼び名を持つ鳥であり、その名前は時代や地域に応じて多少の変化を遂げてきました。
キジ【雉・雉子】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、キジの概要や名前の変遷をカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明・内容 |
|---|---|
| 分類 | キジ目キジ科の鳥 |
| 日本での地位 | 国鳥 |
| 初期の名称 | キギシ |
| 名称の変遷 | 平安時代から「キギシ」 → 時代が下ると「キギス」へ |
| 接尾語「ス」 | 他の鳥の名前にも見られる。「ス(シ)」は朝鮮語由来で、鳥を指す。例:カラス、ウグイス |
| 漢字での表記 | 「雉子」。主に「キギス」や「キギシ」を指す |
| 注意点 | 名前は時代や地域に応じて変化してきた。 |