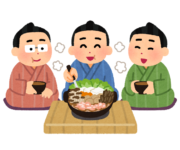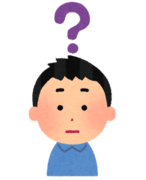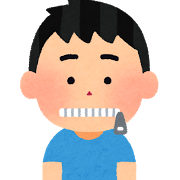提灯は、古くからの日本の照明具で、紙でできた火袋の中に蝋燭を立てて使用するものです。
16世紀末頃、それまでの籠提灯から伸縮自在な箱提灯が登場しました。
現代では、伝統的な蝋燭の代わりに電球を使用することも増えてきています。
この「提灯」という名前は、文字通り「手に提げて歩く灯」を意味しています。
そして「ちょうちん」という読み方は、室町時代に禅家により普及したもので、これは唐音です。
初期の提灯は「挑灯」と書き表されていました。
これは木枠に紙を張り、吊り下げる形の照明具を指していました。
この「挑」という字は「かかげる」という意味を持ちます。
そして、時間が経つにつれ、籠の形をした提灯に紙が張られ、携行しやすいように取っ手が付けられた形、すなわち籠挑灯が登場しました。
要するに、提灯の名前や形状は、その使用方法や機能に基づいて進化してきたのです。
ちょうちん【提灯】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明・内容 |
|---|---|
| 名称 | 提灯(ちょうちん) |
| 定義 | 紙でできた火袋の中に蝋燭を立てて使用する照明具 |
| 語源・名前の由来 | 「手に提げて歩く灯」を意味し、初期は「挑灯」と書かれていた |
| 読み方の起源 | 室町時代の禅家により「ちょうちん」という唐音での読みが普及 |
| 進化 | 16世紀末頃に伸縮自在な箱提灯が登場、現代では電球使用のものも増加 |
| 初期の形状 | 木枠に紙を張り、吊り下げる形状 |
| 「挑」の意味 | 「かかげる」 |
| 籠挑灯 | 篭の形をした提灯で、紙が張られ、携行しやすいように取っ手が付けられた形 |
| 総評 | 提灯の名前や形状は、その使用方法や機能に基づいて進化してきた |