ぬれてであわ【濡れ手で粟】の語源・由来
「濡れ手で粟」という表現は、努力や苦労をせずに大きな利益や報酬を得ることを意味します。 この言葉の背景には、ある簡単な実験や経験が基づいています。 水で濡れた手を使って粟(これは穀物の一種です)を掴むと、手に多くの粟粒が...
 ぬ行
ぬ行「濡れ手で粟」という表現は、努力や苦労をせずに大きな利益や報酬を得ることを意味します。 この言葉の背景には、ある簡単な実験や経験が基づいています。 水で濡れた手を使って粟(これは穀物の一種です)を掴むと、手に多くの粟粒が...
 ぬ行
ぬ行「布」は、もともと動詞「ぬう」や「ヌフ」(縫う)と関連があります。 この「ぬう」に、麻を指す「お」や「ヲ」が付いた言葉「ぬうお」や「ヌフヲ」から派生したと考えられています。 この言葉が時間とともに短縮され、我々が今「布」...
 ぬ行
ぬ行「盗人萩」はマメ科の多年草で、原野によく見られる植物です。 この名前は、植物の特徴的な性質と外見からつけられました。 この植物の種子には細かい鉤状の毛が生えており、これが他の物や人に気づかれないうちに引っかかり、運ばれる...
 ぬ行
ぬ行「ぬかずく」は、ひたいを地につけて礼拝することや、非常に丁寧にお辞儀をすることを意味する言葉です。 この言葉の中の「額(ぬか)」という部分は、古語で「ひたい」を意味しています。 この「額」を「突く」という動作から、直訳す...
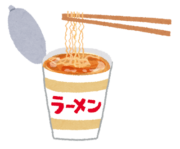 ぬ行
ぬ行「ヌードル」という言葉は、西洋料理における細長い帯状の麺類を総称として用いられるものです。 この言葉の起源は英語の「noodle」にありますが、その背景にはさらに深い歴史が存在します。 元々、ドイツ語に「Knode」とい...
 ぬ行
ぬ行「濡れ場」という言葉は、現代では映画やドラマなどのエンターテインメントにおけるラブシーンや情事の場面を指す言葉として一般的に認識されています。 この言葉の起源は、日本の伝統的な舞台芸術である歌舞伎に遡ります。 歌舞伎にお...
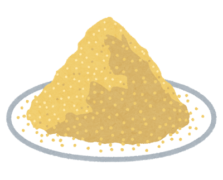 ぬ行
ぬ行「糠喜び」という言葉は、期待外れで、一時的な喜びが実は無駄に終わる状況や、その短い期間の喜びを指す表現です。 「糠」は、玄米を白く精製する際に出る、種の皮や胚芽の粉のことを指します。 この「糠」は、その微細で柔らかい特性...
 ぬ行
ぬ行【意味】 他人を出し抜き、自分だけ先に事を行うこと。 【語源・由来】 「抜け駆け」は、戦争で手柄をたてるために武士がこっそり持ち場を離れて敵陣に攻め込む行為をいう。このことから他人を出し抜く意味が生じた。
 ぬ行
ぬ行「抜き差しならぬ」という言葉は、事態がどうにもならない、または避けられない状況を指す表現です。 この言葉の背景には、刀の抜き差しに関する動作があります。 「抜き差し」とは、刀を鞘から抜いたり、再び鞘に収めたりすることを指...
 ぬ行
ぬ行「濡れ衣」という言葉は、現在では「無実の罪」や「事実に反する噂や誤解」を意味します。 もともと、奈良時代にこの言葉が使われた際には、文字通り雨や海水で濡れた衣服のことを示していました。 しかし、平安時代以降の用法では、言...