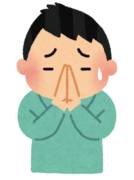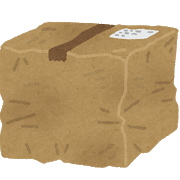「杉」という言葉は、日本の特産である常緑針葉樹を指す名前ですが、その語源や由来についてはいくつかの異なる説が存在します。
一つの説は、杉が長寿命でスクスクと生長する特性を持つことから、「スクスク生える木」という意味を持つ言葉が由来であるというものです。
別の説としては、杉の特徴である真っすぐに伸びる姿から、「すぐ(直)な木」という意味が由来だとされています。
さらに、杉が上へと成長する姿勢から、「すすき(進木)」という言葉が転じて「杉」になったという説も存在します。
最後に、「ス」が細痩を意味し、「キ」が木を意味することから、細痩な木という意味が名前の由来であるとする説もあるのです。
このように、杉の名前の由来には複数の説が存在し、どの説が正しいのかは一つに絞り込むことが難しい状態です。
しかし、これらの説から杉の成長や形状の特徴が名前の由来となっていることが伺えます。
すぎ【杉】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「杉」の名前の由来やその意味、複数存在する説についての情報をカンタンにまとめます。
| 主要ポイント | 詳細・例 |
|---|---|
| 「杉」の基本的な意味 | 日本の特産である常緑針葉樹 |
| 杉の名前の由来の説1 | 杉がスクスクと生長する特性から、「スクスク生える木」という意味が由来 |
| 杉の名前の由来の説2 | 杉の真っすぐに伸びる姿から、「すぐ(直)な木」という意味が由来 |
| 杉の名前の由来の説3 | 杉が上へと成長する姿勢から、「すすき(進木)」が転じて「杉」になった |
| 杉の名前の由来の説4 | 「ス」が細痩を意味し、「キ」が木を意味することから、細痩な木という意味が名前の由来 |
| 複数の説の存在について | 杉の名前の由来には複数の説があり、一つに絞り込むのは難しい。しかし、成長や形状の特徴が名前の由来となっていることが共通していることがわかる |