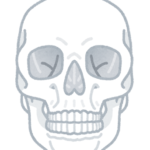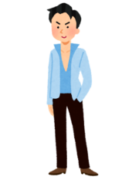「魚」を指す「さかな」という言葉の背景は、日本の歴史と文化の中で変遷してきました。
もともと、魚類を指す言葉は「うお」として知られていました。
しかし、「さかな」という言葉が奈良時代から室町時代にかけて使われるとき、それは魚類を指すものではありませんでした。
実は、この時期に「さかな」とは「塩」や「スモモ」「味噌」などの調味料や食材を意味していました。
その後、江戸時代になると、この「さかな」という言葉の意味が変わり始めます。
「さかな」という言葉が「酒菜」として解釈され、「酒のつまみ」という意味を持つようになりました。
この頃、日常的に酒の際に魚肉がよくつまみとして供されていたため、次第に魚肉自体を「さかな」と呼ぶようになったのです。
現代では、魚類全体を指すときに「魚」という言葉が使われ、酒のつまみを指す時は「肴」という言葉が使われています。
しかし、この「さかな」という言葉の変遷を知ることで、日本の食文化や歴史における魚の位置づけや、言葉の持つ意味の変遷を垣間見ることができます。
さかな【魚】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「さかな」という言葉の変遷や、その背後にある日本の食文化や言葉の意味の変化をカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 初期の意味(うお) | 魚類を指す原始的な言葉 |
| 奈良時代~室町時代 | 「さかな」は調味料や食材(例: 塩、スモモ、味噌)を意味 |
| 江戸時代 | 「さかな」→「酒菜」。酒のつまみ(特に魚肉)を指す意味へ変遷 |
| 現代の用法 | 「魚」= 魚類全体, 「肴」= 酒のつまみ |
| 重要性 | 「さかな」の変遷を通じて、日本の食文化や言葉の持つ意味の変遷を理解 |