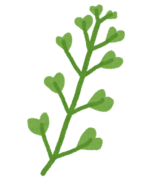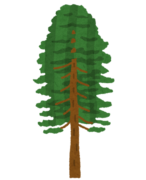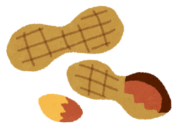薺(なずな)は、春の七草の一つとして知られるアブラナ科の植物です。
この名前「なずな」には、いくつかの説があります。
まず、そのかわいらしい花を見て、撫でてしまいたくなるほどだという意味から「撫菜(なでな)」が起源という説があります。
この「なでな」が言葉の変遷を経て「なずな」となったとされています。
また、別の説として、薺が夏になると枯れてしまう特性から、「夏無(なつな)」が名前の由来であるとも言われています。
この「夏無」も、時代を経ることで「なずな」という言葉に変わったと考えられます。
さらに、薺は「ぺんぺん草」とも呼ばれることがあります。
これは、その形状が三味線を叩くバチに似ていることから、ぺんぺんという音を連想させることからこの名がついたとされています。
これらの説から、薺の名前はその外見や生態、さらには日常の連想から生まれたものであることがわかります。
なずな【薺】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「なずな」の名前の由来やその背景に関する主要な情報をカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 植物名 | 薺(なずな) |
| 分類 | 春の七草の一つ、アブラナ科の植物 |
| 「撫菜」説 | かわいらしい花を「撫でたくなる」から。「撫菜(なでな)」が「なずな」に変わった |
| 「夏無」説 | 夏に枯れる特性から。「夏無(なつな)」が「なずな」に変わった |
| 「ぺんぺん草」 | 三味線のバチに似た形状から「ぺんぺん」という音を連想させる名前 |
| 特徴的な点 | 薺の名前は外見、生態、日常の連想から生まれた |