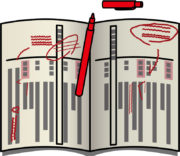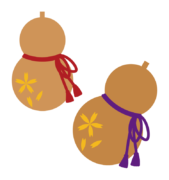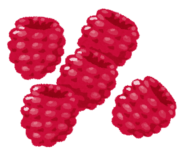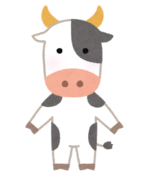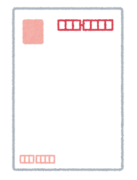「脚色」という言葉は、非常に歴史的な背景を持っています。
語源を見ると、「脚」は「根本」を意味し、「色」は表面に現れること、またはその人物の出自が現れたもの、という意味です。
この言葉が古代中国で初めて使われた際には、官吏登用試験、すなわち科挙の際に提出する身分証明書を指していました。
時が経つにつれ、「脚色」は俳優の役柄や物語の筋書きに手を加えるという意味で用いられるようになりました。
この意味は、日本でも受け入れられ、江戸時代から「仕組み」という言葉とも関連して用いられました。
なお、明治初期までは「きゃくしき」と読むのが一般的で、明治後期から「きゃくしょく」と読むようになったとされています。
さらに、この「脚色」と密接に関わる言葉として「脚本」がありますが、これは「脚色の本」という意味で、明治以降に生まれた言葉だと考えられています。
つまり、古代中国の身分証明から始まり、劇や物語における手法として発展し、最終的には日本でもその用語と概念が広く受け入れられるようになったわけです。
きゃくしょく【脚色】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「脚色」という言葉がどのように起源を持ち、意味が変化してきたか、そして日本でどのように受け入れられたかをカンタンにまとめます。
| キーワード | 説明・詳細 |
|---|---|
| 語源 | 「脚」は「根本」を意味し、「色」は表面に現れることやその人物の出自を指す。 |
| 古代中国 | 脚色が最初に使われた場所で、科挙(官吏登用試験)の際の身分証明書を指していた。 |
| 時代の変遷 | 時が経つにつれて、脚色は物語や劇の筋書きや役柄に手を加える意味で用いられるようになった。 |
| 日本 | 江戸時代から用いられ、「仕組み」とも関連していた。明治初期までは「きゃくしき」と読むのが一般的。 |
| 読み方の変化 | 明治後期から「きゃくしょく」と読むようになった。 |
| 「脚本」の語源 | 「脚色の本」という意味で、明治以降に生まれた言葉。 |