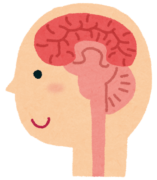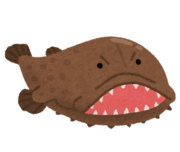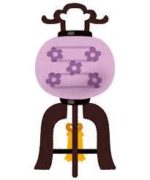「あく(灰汁)」という言葉は日本語において多様な意味を持ちますが、その語源や由来は、もともと植物を焼いて作った灰を水に浸し、その上澄み液を指していました。
この液体はアルカリ性を持っており、古くから洗剤や漂白剤、染色などに使用されていました。
このような灰の上澄み液を使って食品の「えぐみ」や「渋み」を取り除く処理が行われたため、次第に「あく」は、これらの不快な味わいそのものを指すようになりました。
また、この言葉は「飽(あく)」や「あくどい」とも同源で、こちらにも「十分でない」「足りない」といった意味があります。
これが転じて、「あく」には「なじみにくい個性」や「しつこさ」などの意味も含まれるようになりました。
さらに、「あく」は調理過程で特に肉を煮た際に、煮汁の表面に出る白く濁った成分を指すこともあります。
このように、「あく」はその使用状況に応じていくつかの異なる意味を持つようになっていますが、それらは全て元々の「灰の上澄み液」に由来する処理や性質に関連しているわけです。
あく【灰汁】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「あく(灰汁)」についての重要ポイントをわかりやすくカンタンにまとめます。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 語源・由来 | 灰(植物を焼いたもの)を水に浸し、その上澄み液。この液体はアルカリ性。 |
| 古代の用途 | このアルカリ性の液体は、洗剤や漂白剤、染色などに使用されていた。 |
| えぐみ・渋み | 「あく」は食品の「えぐみ」や「渋み」を取り除く処理に使われ、その後、これらの不快な味そのものを指すようになった。 |
| 同源の言葉 | 「飽(あく)」や「あくどい」。これらには「十分でない」「足りない」といった意味があり、「あく」にも「なじみにくい個性」や「しつこさ」の意味が含まれるようになった。 |
| 調理過程での用途 | 特に肉を煮た際に、煮汁の表面に出る白く濁った成分を指す。 |