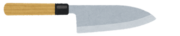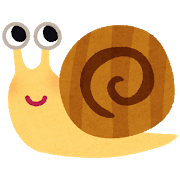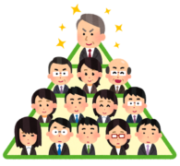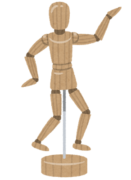「出刃包丁(でばぼうちょう)」は、魚や鳥肉のあら切りに使用される特徴的な形を持つ包丁です。
この名前の由来は、元禄時代の出来事に関連しています。
大阪の堺という場所で、出っ歯の特徴を持った鍛冶職人がこのタイプの包丁を制作したと伝えられています。
その職人の特徴的な「出っ歯」にちなんで、当初この包丁は「出歯包丁」と呼ばれていました。
しかし、この包丁は刃物であり、その役割や形状から「出刃」という言葉が当てはまると考えられたため、時が経つにつれて「出刃包丁」という呼称に変化していったのです。
【出刃包丁】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明・内容 |
|---|---|
| 言葉 | 出刃包丁(でばぼうちょう) |
| 基本の用途 | 魚や鳥肉のあら切り |
| 名前の由来の時代 | 元禄時代 |
| 語源の場所 | 大阪の堺 |
| 関連人物 | 出っ歯の特徴を持った鍛冶職人 |
| 初期の名称 | 「出歯包丁」 |
| 名称の変化の理由 | 包丁の役割や形状から「出刃」という言葉が適しているとされ、「出刃包丁」に変化した |