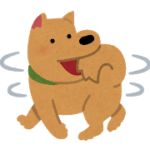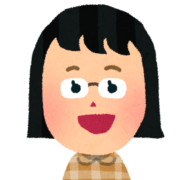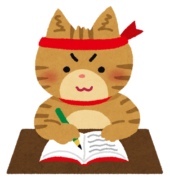「漆喰」という言葉は、日本の特有の塗壁材料を指します。
この塗壁材料は消石灰を主成分として、それにふのりや苦汁(にがり)を加え、更に糸屑や粘土などを配合して練り上げられたものを指します。
広義で見ると、石膏や石灰、セメントを混ぜたモルタル漆喰も指す場合があります。
また、別の名称として「白土(しらつち)」とも呼ばれます。
「漆喰」という名称の語源について考えると、「石灰」の唐音が元となっているとされます。
そして、「漆喰」の漢字は、その音に基づいた当て字として使われるようになったのです。
実際に、江戸時代の文献などを見ると、「漆喰土」や「漆喰塗り」というような表現が存在しているのが確認できます。
興味深い点として、消石灰を主成分とする塗壁は古代から存在していました。
紀元前3000年頃のエジプトでは、このような塗壁がすでに製造・使用されていたと言われています。
しかし、日本での「漆喰」は独自のもので、その起源は奈良時代から平安時代の後半にさかのぼるとされています。
しっくい【漆喰】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「漆喰」に関する重要ポイントをカンタンにまとめます。
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 「漆喰」の定義 | 日本の特有の塗壁材料。消石灰を主成分とし、ふのりや苦汁、糸屑、粘土などを配合して作られる。 |
| 他の名称 | 「白土(しらつち)」とも呼ばれる。 |
| 広義の「漆喰」 | 石膏や石灰、セメントを混ぜたモルタル漆喰も含まれる場合がある。 |
| 語源と漢字 | 「石灰」の唐音が元となっており、当て字として「漆喰」という漢字が使われるようになった。 |
| 江戸時代の文献 | 「漆喰土」や「漆喰塗り」などの表現が存在している。 |
| 歴史的背景 | 消石灰を主成分とする塗壁は古代からあり、紀元前3000年のエジプトでも使用されていた。日本の「漆喰」は独自のもので、奈良から平安時代の後半に起源がある。 |