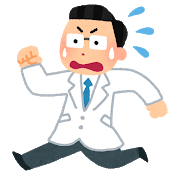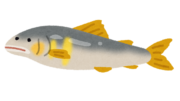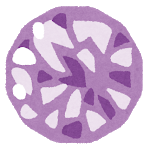「秋」は、日本においては四季の第三の季節とされ、9月から11月までを指します。
この季節は、多くの穀物や果物の収穫期であり、涼しい風が吹くことが多い一方で、台風などにより天候が変わりやすいのも特徴です。
語源と由来に関しては複数の説が存在しています。
一つの説は、稲が成熟する様子を指す「黄熱(あかり)」から来ているというものです。
成熟した稲は黄金色に輝き、これが「秋」という言葉に繋がっているとされています。
また、もう一つの説は「清明(あきらか)」から来ているというものです。
この説では、秋の空が澄み渡って清らかであることが由来とされています。
さらに、「飽き満ち(あきみつる)」から来ているという説もあります。
これは、秋には多くの穀物が収穫され、飽きるほどに多くの食物が得られることを指しています。
最後に、草木の葉が赤く染まる紅葉から「紅く(あかく)」が転じたという説もあるようです。
いずれの説も、秋という季節の多様な特性や風物を象徴しており、そのどれもが「秋」の言葉に色濃く反映されています。
あき【秋】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「秋」の語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 日本における定義 | 四季の第三の季節で、9月から11月まで。 |
| 主な特性 | 穀物や果物の収穫期、涼しい風、変わりやすい天候(例:台風)。 |
| 語源説1 | 「黄熱(あかり)」から来ている。稲が成熟して黄金色になる様子が由来。 |
| 語源説2 | 「清明(あきらか)」から来ている。秋の空が澄み渡って清らかであることが由来。 |
| 語源説3 | 「飽き満ち(あきみつる)」から来ている。多くの穀物が収穫され、飽きるほどに多くの食物が得られることが由来。 |
| 語源説4 | 葉が赤く染まる紅葉から「紅く(あかく)」が転じたという説も存在。 |