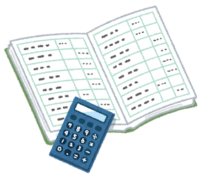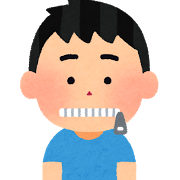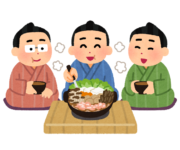「知事」という言葉は、サンスクリット語の「karamadana」から派生しています。
「知」の部分は「つかさどる」を、そして「事」の部分は「事務」をそれぞれ意味しています。
この組み合わせで、「事を知ること」や「つかさどること」という意味が形成されました。
当初、この言葉は仏教の文脈で使用され、寺院の中での役職、特に庶務を管理する役職を指していました。
その後、寺院の事務がより複雑になるにつれて、6つの知事の役職、すなわち都寺、監寺、副寺、維那、展座、直歳が設けられました。
そして、宋の時代にこの言葉はさらに発展し、州や県の長官、すなわち行政のトップを指す名称として使われるようになりました。
この用法が日本にも取り入れられ、現在の都道府県の知事の職名として確立されたのです。
ちじ【知事】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 説明・内容 |
|---|---|
| 言葉 | 知事 |
| 語源 | サンスクリット語の「karamadana」 |
| 意味の成り立ち | 「知」は「つかさどる」、「事」は「事務」。組み合わせて「事を知ること」や「つかさどること」を意味。 |
| 初期の使用文脈 | 仏教の文脈、特に寺院内の庶務を管理する役職 |
| 6つの知事の役職 |
|
| 宋の時代の用法 | 州や県の長官、行政のトップとして |
| 日本における現在の用法 | 都道府県の知事の職名として |