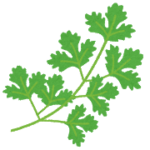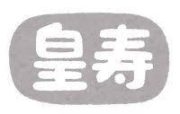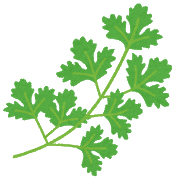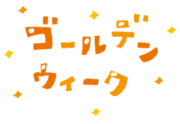「コノシロ」という名前の由来は、大量に獲れることから「飯の代わりにする魚」を意味する「飯代魚」として名付けられたという説がある一方で、子供の健康な成長を祈ってこの魚を地中に埋める風習から「児の代」と呼ばれるようになったという説も存在します。
さらに、「コノシロを焼く」は言葉として「この城を焼く」と似ているため、江戸時代の武士たちの間では、この表現を避ける傾向がありました。
この魚に関連する漢字表記はいくつか存在します。
「鮗」は、特に冬に多く獲れることを示しています。
一方「鰶」の漢字は、秋の祭りで「鮓」の材料として利用されることや、狐が好んで食べることから、狐の神である御稲荷さんへの供え物として用いられたことに関連しています。
「鯯」の漢字は日本書紀にも記載がありますが、具体的な語源についてははっきりしていません。
「鱅」は、コノシロを焼くと発する独特の臭い、特に死体を焼いた時のような強い臭いに由来しているとされています。
【鮗・鰶・鯯・鱅】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

表を使って、「コノシロ」の名前の起源や関連する漢字とその背景などの主要なポイントをカンタンにまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前の由来説1 | 大量に獲れるため「飯の代わりにする魚」→「飯代魚」から |
| 名前の由来説2 | 子供の健康な成長を祈る風習で地中に埋める→「児の代」から |
| 言葉の似ている点 | 「コノシロを焼く」は「この城を焼く」に似ており、江戸時代の武士は避ける傾向 |
| 漢字「鮗」 | 冬に多く獲れる特性を示す |
| 漢字「鰶」 | 秋の祭りの「鮓」材料、また狐の好物として御稲荷さんへの供え物との関連 |
| 漢字「鯯」 | 日本書紀に記載あり。具体的な語源は不明 |
| 漢字「鱅」 | コノシロを焼く際の独特の臭い、特に死体を焼いた際の強い臭いに由来 |